
|

|
太陽系は、太陽とその周りをまわる9つの惑星、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星と、これらの惑星をまわる衛星、火星と木星の間にある小惑星、その他の隕石、彗星、塵などから成立っている。中心の太陽は、質量で太陽系の99.866%を占めており、残りの僅か0.134%を木星が70%、土星が20%占めている。小惑星は5,000個以上発見されているが、どの位あるのか未だ分かっていない。
惑星のうち水星、金星、地球、火星は太陽の近くに密集しており、主に岩石質からなるため惑星個々の密度が高く「地球型惑星」と呼ばれる。木星、土星、天王星、海王星は太陽から遠く、巨大な惑星であるが密度は低く、水素、ヘリュームなど軽い元素からなり、「木星型惑星」と呼ばれる。木星型惑星は多くの衛星や環をもっている。冥王星は木星型惑星に似た性質をもつが、太陽をまわる軌道にズレ(離心率)が大きく、また固有の特徴も持つので、通常は木星型惑星には含めない。
太陽系は、特に巨大な太陽を中心に、惑星相互の力学的作用から現在の形ができたと考えられるが、例えば月が現在でもほんの少しづつ地球から遠ざかっているように、地球の年齢45億年のような長い尺度で考えると、今の形もほんのいっときの、そしてかりそめの姿なのかも知れない。
< 水 星 > Mercury
 太陽に一番近い惑星であり、いくつかの特異な性質を持っている。軌道の離心率が冥王星に次いで大きく、遠日点と近日点の差は2,400万kmにも及ぶ。黄道面に対する軌道の傾斜は約7度あり、これも冥王星に次いで大きい。自転軸は軌道面に対してほぼ垂直である。水星は小さな惑星で直径は4,878km、月より少し大きいが地球の1/3程度であり、木星の衛星ガニメデや土星の衛星タイタンの方が大きい。平均密度は地球や金星とほぼ同じである。直径は火星より30%位小さいが、密度が高いため表面重力は火星とほぼ同じである。このことから水星内部の核の占める割合が大きいこと、核の主成分が重い元素を多く含んでいることが想定される。水星の表面はレゴリスで覆われていると見られている。水星の磁場は地球に似ているが磁場の強さは地球の1%しかない。
太陽に一番近い惑星であり、いくつかの特異な性質を持っている。軌道の離心率が冥王星に次いで大きく、遠日点と近日点の差は2,400万kmにも及ぶ。黄道面に対する軌道の傾斜は約7度あり、これも冥王星に次いで大きい。自転軸は軌道面に対してほぼ垂直である。水星は小さな惑星で直径は4,878km、月より少し大きいが地球の1/3程度であり、木星の衛星ガニメデや土星の衛星タイタンの方が大きい。平均密度は地球や金星とほぼ同じである。直径は火星より30%位小さいが、密度が高いため表面重力は火星とほぼ同じである。このことから水星内部の核の占める割合が大きいこと、核の主成分が重い元素を多く含んでいることが想定される。水星の表面はレゴリスで覆われていると見られている。水星の磁場は地球に似ているが磁場の強さは地球の1%しかない。
水星に接近した探査機としては1974年3月のマリナー10号がある。マリナー10号は水星に3回接近し7,000枚に及ぶ画像を送り返した。ただし、その多くは地球から撮影した月の望遠鏡写真程度の精度である。
 宵の明星、明けの明星として親しまれ、地球に最も近づく惑星である。太陽系の中で最も離心率が小さく真円に近い楕円である。軌道の傾斜は冥王星、水星に次いで大きい。金星は公転方向と逆方向(北極からみて右回り)に自転しており、自転周期(243日)が公転周期(224日)より長いから、地球の感覚で言えば一日が一年より長いことになる。この数値から地球の尺度で計算すると金星の一日は地球での116.8日にあたる。面白いことに、金星と地球の会合周期は584日であり、これは金星の一日の5倍にあたる。このため金星が地球に近づくときは、いつも同じ面を地球に向けている。これも地球と金星の相互の力学的作用(潮汐力)の結果生じたものと考えられる。金星は地球と直径や質量の点ではきわめて似ている。しかし、磁場がほとんどない。硫黄を含む濃硫酸の厚い雲で覆われており、表面温度は鉛も融けてしまう高温420〜485度C、気圧は深海1,000mに相当する90気圧というきわめて過酷な世界である。大気の主成分は二酸化炭素で水分は0.1%しかない。また、火山活動が頻繁に起きていると推測されている。
宵の明星、明けの明星として親しまれ、地球に最も近づく惑星である。太陽系の中で最も離心率が小さく真円に近い楕円である。軌道の傾斜は冥王星、水星に次いで大きい。金星は公転方向と逆方向(北極からみて右回り)に自転しており、自転周期(243日)が公転周期(224日)より長いから、地球の感覚で言えば一日が一年より長いことになる。この数値から地球の尺度で計算すると金星の一日は地球での116.8日にあたる。面白いことに、金星と地球の会合周期は584日であり、これは金星の一日の5倍にあたる。このため金星が地球に近づくときは、いつも同じ面を地球に向けている。これも地球と金星の相互の力学的作用(潮汐力)の結果生じたものと考えられる。金星は地球と直径や質量の点ではきわめて似ている。しかし、磁場がほとんどない。硫黄を含む濃硫酸の厚い雲で覆われており、表面温度は鉛も融けてしまう高温420〜485度C、気圧は深海1,000mに相当する90気圧というきわめて過酷な世界である。大気の主成分は二酸化炭素で水分は0.1%しかない。また、火山活動が頻繁に起きていると推測されている。
金星に関連した探査機としては、1962年のマリナー2号(米)1970年のベネラ7号(ソ連)、またベネラ8号に続き、1975年10月のベネラ9号と10号が、また、1982年3月にはベネラ13号と14号が金星に軟着陸し、各地点での写真を送り返した。1978年12月には米国のパイオニアビーナス号が金星を回る軌道に乗り、93%のマップを撮った。1985年にはソ連のベネラ15、16号が北半球(全表面の25%)を解像度1〜2kmで撮影した。このほか、1984年にベガ1、2号がハレー彗星に向かう途中金星を通過した際、着陸船を降下させている。また、今年4月に土星探査船カッシーニが土星に向かう旅程のなかで一回目の接近を行う。
 地球のことはさておき、ここでは今後話題になるであろう地球の唯一の衛星、月に関する話題を取り上げてみよう。月の起源については多くの仮説があり、分裂説(地球と月は親子とする説)、捕獲説(地球が他の天体を捕獲して衛星としたとする説)、集積説(地球と月は兄弟とする説)に大別できた。しかし、アポロやルナが持ち帰った岩石の研究で総崩れとなった。その理由は地球と月に含まれる元素とその配分が、似たところと明らかに異なるところがあり、いずれの説でも説明できないところからきている。1980年代後半に唱えられた巨大衝突説(Giant impact)は、これらを補うものとして新たに登場した。
地球のことはさておき、ここでは今後話題になるであろう地球の唯一の衛星、月に関する話題を取り上げてみよう。月の起源については多くの仮説があり、分裂説(地球と月は親子とする説)、捕獲説(地球が他の天体を捕獲して衛星としたとする説)、集積説(地球と月は兄弟とする説)に大別できた。しかし、アポロやルナが持ち帰った岩石の研究で総崩れとなった。その理由は地球と月に含まれる元素とその配分が、似たところと明らかに異なるところがあり、いずれの説でも説明できないところからきている。1980年代後半に唱えられた巨大衝突説(Giant impact)は、これらを補うものとして新たに登場した。
”地球が現在の大きさに近くなったとき、火星とほぼ同じ大きさの天体が地球をかすめるように衝突し、地球と天体の物質が地球を回る軌道上に投げ出された。衝突した天体は地球と合体したが、投げ出された物質は急速に集まって月になった”これが巨大衝突説のあらましである。近年のコンピュータシミュレーションの進歩は、このような仮説をも検証できるところまで進んでいるが、この仮説にもまだ疑問点がある。
地球には月の引力で海水が引っ張られ満潮や干潮を生む潮汐作用がある。この作用は地球や月にも僅かずつの影響を与えている。月は現在3cm/年地球から遠ざかっていると言われ、また地球の自転速度は10万年に1秒遅くなると言われている。逆に、46億年前の地球の一日は10時間以下と推定できるとも言われており、太古の地球の一日が短かったことは、古生代のサンゴの化石やオウムガイの化石の日輪、年輪からも証明できた。月には大気が存在せず風化作用が起きない。このことは同時代にできた地球の姿を推定できる貴重な存在でもある。
月に関するさらに詳しい情報は、ルナ・プロスペクターを通して知ることができるだろう。
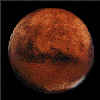 火星の姿はマーズパスファインダとマーズグローバルサーベイヤを通して多くの解説がなされた。ここでは基本的な情報をまとめておこう。火星の太陽からの距離は1.38〜1.67AUであり、太陽系惑星の中で3番目に離心率が大きい。このため比較的離心率の小さい地球との接近には大接近と小接近が生ずる。自転周期24時間37分22秒、自転軸の傾き約25度は地球とよく似ている。このため火星では地球とほぼ同じに一日が繰り返され、四季の変化がある。但し、火星の公転周期は687日だから、それぞれの季節は地球のそれの約1.9倍長いことになる。フォボス(Phobos)とデイモス(Deimos)という二つの小さな衛星を持ち、半径は地球の半分強、体積は1/6、質量は1/10でかなり小さい。火星は平均密度が地球型惑星の中では目立って低く、これまで火星には磁気がないとされてきたが、今回の探査では磁気が確認された。このことは火星内部の構造を知る上で重要な要素である。
火星の姿はマーズパスファインダとマーズグローバルサーベイヤを通して多くの解説がなされた。ここでは基本的な情報をまとめておこう。火星の太陽からの距離は1.38〜1.67AUであり、太陽系惑星の中で3番目に離心率が大きい。このため比較的離心率の小さい地球との接近には大接近と小接近が生ずる。自転周期24時間37分22秒、自転軸の傾き約25度は地球とよく似ている。このため火星では地球とほぼ同じに一日が繰り返され、四季の変化がある。但し、火星の公転周期は687日だから、それぞれの季節は地球のそれの約1.9倍長いことになる。フォボス(Phobos)とデイモス(Deimos)という二つの小さな衛星を持ち、半径は地球の半分強、体積は1/6、質量は1/10でかなり小さい。火星は平均密度が地球型惑星の中では目立って低く、これまで火星には磁気がないとされてきたが、今回の探査では磁気が確認された。このことは火星内部の構造を知る上で重要な要素である。
火星の赤い色は昔から不吉な色とされ、ローマ神話の軍神 Marsの名が付けられてきた。火星探査の失敗の歴史もこれに負うところがあるのだろうか。しかし、マーズパスファインダ、マーズグローバルサーベイヤによる輝かしい成果は、これまで不明とされてきたことの解決に役立つことだろう。
火星についてのこれ以上の情報は「火星探査のページ」を参照。
 太陽系最大の惑星。赤道半径は地球の約11倍、総体の質量は約318倍。主に軽い元素でできているため、平均密度は地球型惑星に比して格段に低い。自転周期は赤道付近で約9時間50分、中緯度付近で9時間55分という測定データがあるが、この違いは赤道付近の雲が強い偏西風に流されているためで、真の自転周期は9時間55分という説がある。自転周期が速いことからその姿はやや扁平である。木星の表面は厚い雲に覆われており内部は見えないが、観測衛星のデータによれば大部分が水素で少量のヘリュームが混ざっている。水素は高圧の下で液体分子状になり、さらに高圧(300万気圧)の下では液体金属状になると言われる。この変換点(雲から下約2万km)の温度は絶対温度1万度に達すると言われるから、木星の内部は著しい高圧、高温の世界である。木星がもう少し大きな天体だったら、中心部の温度と圧力がもっと高くなり、核融合が起きて太陽のような恒星になったかもしれない。木星は太陽になりそこねた天体である。木星はまた近年シューメイカーレヴィの九つの星が引き込まれ衝突したことでも知られている。木星には半径の約3倍くらいのところまで薄い環が存在することが探査の結果判明した。木星の環は反射能が低いことから、土星の環と異なり岩石質と言われている。
太陽系最大の惑星。赤道半径は地球の約11倍、総体の質量は約318倍。主に軽い元素でできているため、平均密度は地球型惑星に比して格段に低い。自転周期は赤道付近で約9時間50分、中緯度付近で9時間55分という測定データがあるが、この違いは赤道付近の雲が強い偏西風に流されているためで、真の自転周期は9時間55分という説がある。自転周期が速いことからその姿はやや扁平である。木星の表面は厚い雲に覆われており内部は見えないが、観測衛星のデータによれば大部分が水素で少量のヘリュームが混ざっている。水素は高圧の下で液体分子状になり、さらに高圧(300万気圧)の下では液体金属状になると言われる。この変換点(雲から下約2万km)の温度は絶対温度1万度に達すると言われるから、木星の内部は著しい高圧、高温の世界である。木星がもう少し大きな天体だったら、中心部の温度と圧力がもっと高くなり、核融合が起きて太陽のような恒星になったかもしれない。木星は太陽になりそこねた天体である。木星はまた近年シューメイカーレヴィの九つの星が引き込まれ衝突したことでも知られている。木星には半径の約3倍くらいのところまで薄い環が存在することが探査の結果判明した。木星の環は反射能が低いことから、土星の環と異なり岩石質と言われている。
木星には16の衛星が確認されている。1610年にガリレオが発見したイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストが有名でガリレオ衛星と呼ばれる。
<イオ> 木星に最も近い衛星である。ボイジャー1、2号の観測の結果、イオに活火山が10個確認されたが、その火山活動の規模は地球の火山に比して桁外れに大きく、今年6月に観測史上最大の噴煙が見られた。イオは地球型惑星と似ているが、水や氷は存在しないと思われている。
<エウロパ> 月より15%くらい小さい星で、その本体は岩石と水の氷、表面は氷で覆われていると信じられている。ボイジャー2号の画像からは、エウロペ表面がオレンジ色を背景に、マスクメロンのように筋が入っていることが分かる。クレーターもあるがきわめて少ない。これはこの衛星の表面が比較的新しく形成されたか、あるいは氷の作用によって地表が変えられたとも考えられ、水の存在が生命の存在を期待させる楽しみな星の一つである。
<ガニメデ> 太陽系最大の衛星である。水星よりも1割弱大きく、平均密度はかなり低い。水の氷と岩石でできていると推定されているが大気は無い。ガニメデはクレーターが多い暗い地域と、多数の溝を中心とする明るい地域が判然としている。溝は内部からの氷の噴出によって作られ、クレーターを破壊したとも考えられる。
<カリスト> 水星とほぼ同じ大きさ。水の氷の割合はガニメデより大きいと思われている。表面はギッシリとクレーターで覆われており、興味あることに多層の環状の縞がいくつか見られる。その最大のものは経3,000kmを超える。
木星を調査した探査機としては、1973、1974年のパイオニア10、11号、1979年のボイジャー1、2号がある。また、現在ガリレオ宇宙船が木星とその衛星の調査を行っている。
 美しい環を持ち、太陽系の中では木星に次ぐ大きな惑星であり、赤道半径は地球の9倍程もある。平均密度は最低で木星の1/2程度、ボイジャーによる測定では自転速度は10時間39分とかなり速い。このため木星と同様扁平な球状を示している。土星を作っている元素は、木星と同じ水素とヘリュームであるが、質量は木星が地球の318倍であるに対して土星は95倍しかない。このことから土星内部は深くまで水素の液状分子状であると思われる。土星は太陽から受ける熱の2.5倍ものエネルギーを放出している。ボイジャーは土星の内部エネルギーが過剰であることも確かめた。1979年パイオニア11号は土星に磁場と放射能帯があることを示し、ボイジャーは磁場の強さが地球の1,000倍であることを確かめた。但し、土星は地球より半径が大きいので地表上での磁場の強さは地球表面よりやや小さい程度であり、磁場の極は木星と共に南北が地球とは逆である。磁気圏は土星半径の21倍ほどまで広がり、先端では荷電粒子が捕捉されて、地球で言うバン・アレン帯のような放射能帯がある。
美しい環を持ち、太陽系の中では木星に次ぐ大きな惑星であり、赤道半径は地球の9倍程もある。平均密度は最低で木星の1/2程度、ボイジャーによる測定では自転速度は10時間39分とかなり速い。このため木星と同様扁平な球状を示している。土星を作っている元素は、木星と同じ水素とヘリュームであるが、質量は木星が地球の318倍であるに対して土星は95倍しかない。このことから土星内部は深くまで水素の液状分子状であると思われる。土星は太陽から受ける熱の2.5倍ものエネルギーを放出している。ボイジャーは土星の内部エネルギーが過剰であることも確かめた。1979年パイオニア11号は土星に磁場と放射能帯があることを示し、ボイジャーは磁場の強さが地球の1,000倍であることを確かめた。但し、土星は地球より半径が大きいので地表上での磁場の強さは地球表面よりやや小さい程度であり、磁場の極は木星と共に南北が地球とは逆である。磁気圏は土星半径の21倍ほどまで広がり、先端では荷電粒子が捕捉されて、地球で言うバン・アレン帯のような放射能帯がある。
土星の環は現在AからGまで7つに分けられている。内側からD−C−B−A−F−G−Eであり、B環とA環の間にカッシーニ間隙と呼ばれる空隙がある。F環は1979年にパイオニア11号が、G環は1980年にボイジャー1号が、E環は1966年に地上から発見したものである。環の間の空隙にはAとFとの間にエンケの空隙と言われるものもあるが、現在ではこれら空隙には全く物質がないわけではなく、薄い細い環があることが分かっている。ボイジャーの観測では土星の環は厚さ数10〜数100m、これを構成する物質はA、B、C環で最大約10m、ほとんどがメートルあるいはセンチレベル、F環では非常に小さい粒の集団であることが分かっている。ボイジャーはまたB環上にスポークと呼ばれるいわゆる自転車のスポークに似た模様を発見した。これの解明はこんごの課題である。
土星には18の衛星が発見されている。なお、土星には現在探査船カッシーニが向かっている。
<タイタン> 太陽系第2の大きさの衛星で水星より大きい。岩石質と氷が約半分づつで構成されていると考えられている。大気の主成分は窒素、大気圧は1,500ミリバール(地球の1.5倍)、表面温度は−180度C。タイタンの地表付近ではメタンが水蒸気のように雲になり雨となり、湖や海を作っているのではないかと期待されている。タイタンは生命の存在までは無理としても、自然が作る有機物の存在が期待できる面白い存在である。
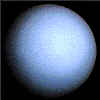 1781年に発見された天王星には奇妙な特徴がある。それは自転軸が公転軌道面の垂線に対して98度も傾いていることである。この惑星は公転軌道上を横倒しになって転げ回っている。公転周期は84年、ボイジャー2号の測定による自転周期は17.2時間。大気の構成は水素、ヘリューム、メタンからなる。ボイジャーの観測によれば、このとき太陽熱を受けていた南極地方と受けられない赤道地帯での温度差がほとんどなかった。雲の動きは東西方向であり、自転の影響が温度差による影響を凌ぎ、イメージの解析では雲の動きが最大200m/秒に達することが分かった。風による対流もないとすると太陽から受けた熱はどのようにして赤道まで伝えられるのだろうか。天王星にも磁場がある。しかし磁場の軸が自転軸に対して60度も傾いている。ボイジャーは磁場のあるところにできるオーロラも確認した。天王星にも11本の環がある。厚さは150m程度で、土星の環と異なる多くの点がある。ボイジャーの観測によれば形、幅、密度が一様ではなく、環にそって大きく揺らいでおり、離心率の大きな楕円形のものもある。環を構成する粒子が暗いのもひとつの特徴である。
1781年に発見された天王星には奇妙な特徴がある。それは自転軸が公転軌道面の垂線に対して98度も傾いていることである。この惑星は公転軌道上を横倒しになって転げ回っている。公転周期は84年、ボイジャー2号の測定による自転周期は17.2時間。大気の構成は水素、ヘリューム、メタンからなる。ボイジャーの観測によれば、このとき太陽熱を受けていた南極地方と受けられない赤道地帯での温度差がほとんどなかった。雲の動きは東西方向であり、自転の影響が温度差による影響を凌ぎ、イメージの解析では雲の動きが最大200m/秒に達することが分かった。風による対流もないとすると太陽から受けた熱はどのようにして赤道まで伝えられるのだろうか。天王星にも磁場がある。しかし磁場の軸が自転軸に対して60度も傾いている。ボイジャーは磁場のあるところにできるオーロラも確認した。天王星にも11本の環がある。厚さは150m程度で、土星の環と異なる多くの点がある。ボイジャーの観測によれば形、幅、密度が一様ではなく、環にそって大きく揺らいでおり、離心率の大きな楕円形のものもある。環を構成する粒子が暗いのもひとつの特徴である。
天王星には15の衛星が発見されている。このうちボイジャー2号によって発見された衛星が10ある。従来型の衛星が反射能が大きく明るいのに対して、新たに発見された衛星はどれも非常に暗い。この暗さの理由も証明できてはいない。天王星の衛星で注目される一つにミランダがある。その表面はきわめて複雑怪奇なさまを見せている。その理由もまだ分かっていない。
天王星にはまだまだ分からないことが多い。これらが解明できるようになるのは何時のことだろうか。
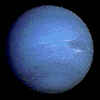 海王星は離心率が金星に次いで小さくほぼ円に近い軌道を持っている。自転軸は29度の傾きである。1989年8月25日、ボイジャー2号が海王星に接近した。この観測によって自転周期が16.11時間であることが分かった。平均密度は木星型惑星の中では最大で、内部が水より岩石質の方が多いことを示唆している。海王星の磁軸は自転軸に対して46.8度も傾き、しかも南側に大きくずれていることが分かった。海王星が天王星と同じく青く見えるのは、大気中のメタンが赤い光を吸収するためである。大気は水素とヘリュームが主体で、メタン、メタンの光分解で生じた炭化水素、アンモニア、硫化水素などの雲がありきわめて活発に活動している。海王星の表面には気流に起因する黒斑や白斑が目立つ。海王星には4本の環がある。外縁の環には部分的に密度の高い厚いところがある。環の粒子は小さくダスト粒子を多く含むようである。海王星の衛星はトリトンとネレイドの二つが知られていたが、ボイジャー2号は新たに6個の衛星を発見した。トリトンとネレイドは軌道の傾きが大きく、トリトンでは157度(23度で逆行している。つまり海王星上から見ると西から昇って東に沈む)、ネレイドでは29度もある。トリトンの逆行性は地球の月が次第に離れてゆくのとは逆に、遠い先には海王星に引きつけられ壊されてしまうとも言われている。ネレイドは離心率が著しく大きく海王星中心からの距離は遠地点は近地点の約7倍にもなる。
海王星は離心率が金星に次いで小さくほぼ円に近い軌道を持っている。自転軸は29度の傾きである。1989年8月25日、ボイジャー2号が海王星に接近した。この観測によって自転周期が16.11時間であることが分かった。平均密度は木星型惑星の中では最大で、内部が水より岩石質の方が多いことを示唆している。海王星の磁軸は自転軸に対して46.8度も傾き、しかも南側に大きくずれていることが分かった。海王星が天王星と同じく青く見えるのは、大気中のメタンが赤い光を吸収するためである。大気は水素とヘリュームが主体で、メタン、メタンの光分解で生じた炭化水素、アンモニア、硫化水素などの雲がありきわめて活発に活動している。海王星の表面には気流に起因する黒斑や白斑が目立つ。海王星には4本の環がある。外縁の環には部分的に密度の高い厚いところがある。環の粒子は小さくダスト粒子を多く含むようである。海王星の衛星はトリトンとネレイドの二つが知られていたが、ボイジャー2号は新たに6個の衛星を発見した。トリトンとネレイドは軌道の傾きが大きく、トリトンでは157度(23度で逆行している。つまり海王星上から見ると西から昇って東に沈む)、ネレイドでは29度もある。トリトンの逆行性は地球の月が次第に離れてゆくのとは逆に、遠い先には海王星に引きつけられ壊されてしまうとも言われている。ネレイドは離心率が著しく大きく海王星中心からの距離は遠地点は近地点の約7倍にもなる。
 1930年に発見された冥王星は、太陽からの距離が最大49.4AU(遠日点)、最小29.7AU(近日点)という太陽系惑星の中で離心率最大の惑星である。そして近日点前後には海王星の内側に約1億kmも入り込む。しかし、冥王星の軌道は海王星の軌道に対して約15.4度傾いていることから衝突することは避けられている。現在冥王星は海王星の内側にあり、この状態は1999年3月まで続く。冥王星は光度が低いので地上からの観測が難しく、また探査機も近づいたことがないので詳しいことは分からない。冥王星には1978年になって発見されたカロンと呼ばれる極端に近接した衛星がある。カロンは相互の潮汐作用から常に冥王星に対して同じ面を向け、軌道はほぼ完全な円形であり、冥王星の自転とカロンの公転、自転が同期している。カロンは衛星としては極端に大きく冥王星の半分程もあり、衛星というより二重惑星と言った方が良いかも知れない。冥王星はこのカロンの観測によって多くのことが推定できるようになった。例えば冥王星は公転軌道の垂線に対して自転軸が118度も傾いていて、海王星と同様公転軌道上を転げ回っていることが分かった。また、1985年1月から1990年10月まで冥王星の太陽面にカロンが入る食現象が起きた。この現象は124年ごとに起きるが冥王星発見以来初めてのことになる。この食現象を精密に分析することによって、冥王星の姿がかなり絞られてきた。また、1988年には乙女座12等星とのえんぺい(掩蔽)現象が起きた。この観測で冥王星の大気の状態がおぼろげながらも分かってきた。しかし、いずれもまだ推測の域を越えていない。冥王星はまだまだ未知の星である。
1930年に発見された冥王星は、太陽からの距離が最大49.4AU(遠日点)、最小29.7AU(近日点)という太陽系惑星の中で離心率最大の惑星である。そして近日点前後には海王星の内側に約1億kmも入り込む。しかし、冥王星の軌道は海王星の軌道に対して約15.4度傾いていることから衝突することは避けられている。現在冥王星は海王星の内側にあり、この状態は1999年3月まで続く。冥王星は光度が低いので地上からの観測が難しく、また探査機も近づいたことがないので詳しいことは分からない。冥王星には1978年になって発見されたカロンと呼ばれる極端に近接した衛星がある。カロンは相互の潮汐作用から常に冥王星に対して同じ面を向け、軌道はほぼ完全な円形であり、冥王星の自転とカロンの公転、自転が同期している。カロンは衛星としては極端に大きく冥王星の半分程もあり、衛星というより二重惑星と言った方が良いかも知れない。冥王星はこのカロンの観測によって多くのことが推定できるようになった。例えば冥王星は公転軌道の垂線に対して自転軸が118度も傾いていて、海王星と同様公転軌道上を転げ回っていることが分かった。また、1985年1月から1990年10月まで冥王星の太陽面にカロンが入る食現象が起きた。この現象は124年ごとに起きるが冥王星発見以来初めてのことになる。この食現象を精密に分析することによって、冥王星の姿がかなり絞られてきた。また、1988年には乙女座12等星とのえんぺい(掩蔽)現象が起きた。この観測で冥王星の大気の状態がおぼろげながらも分かってきた。しかし、いずれもまだ推測の域を越えていない。冥王星はまだまだ未知の星である。
 HOME
HOME